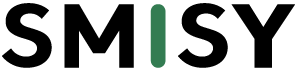高齢化社会の進展に伴い、認知症や知的障害により判断能力が不十分な方の増加が見込まれています。こうした状況で「成年後見人」という言葉を聞いたことがあるかもしれませんが、その具体的な役割や選び方については、まだよく知られていない部分が多いのではないでしょうか。本記事では、成年後見人の基本的な役割や職務、成年後見制度の詳細について、わかりやすく解説します。
目次
1.成年後見人とは?
「成年後見人」という言葉は聞いたことがあるものの、具体的な役割や選任方法についてはあまり詳しく知らない方も多いのではないでしょうか?成年後見人は、「成年後見制度」に基づいて、認知症や知的障害などで判断能力が不十分な人の代わりに法律行為を行う人物です。例えば、契約の締結や解除、財産の管理を本人の代わりに行い、法律的な観点から本人を保護・支援します。
成年後見人が必要となる状況には以下のような例があります。
- 認知症の親が同じものを何度も購入してしまう
- 判断能力が衰えた人の財産を親族が勝手に使用している
- 遺産分割協議を進めたいが、被相続人の判断能力が不十分
- 認知症のため、親の不動産を売却して施設入所費用を捻出したいが、本人が手続きを行うのが難しい
- 知的障害を抱えた親族がいる
この記事では、成年後見人の役割、適任者、選任手続き、かかる費用などについて詳しく解説します。
2.成年後見人制度の種類
成年後見人制度には「法定後見制度」と「任意後見制度」という2つの種類があります。どちらを選ぶかは、成年被後見人(後見が必要な人)の判断能力に基づいて決まります。判断能力が不十分な成年被後見人を「本人」と呼びます。
法定後見制度は、本人の判断力が不十分と判断される場合に利用され、家庭裁判所が適任者を選びます。法定後見には「後見」、「保佐」、「補助」の3つの形態があり、権限の範囲が異なります。具体的には、補助人から後見人へと権限が広がります。選択は本人の認知症や障害の度合いに応じて決まります。
任意後見制度は、判断力がまだ十分なうちに任意後見人を選び、支援内容を事前に決める制度です。任意後見契約は「公正証書」で結ぶ必要があります。任意後見の効力は、本人の判断力が低下した後から発揮されます。
3.成年後見人になれる人、職務と権限
(1)成年後見人になるには?
成年後見人には特別な資格は必要ありません。親族のほか、弁護士や司法書士、社会福祉士などの専門家も選任されることがあります。以下の条件に該当する人は成年後見人になれません。
- 未成年者
- 破産者
- 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
- 成年被後見人に対して訴訟を起こしている人、その配偶者及び直系血族
- 行方不明の人
成年後見人が一度決まると変更は容易ではありませんが、特例として以下の場合に変更が可能です
①成年後見人が辞任する場合
成年後見人が辞任を申し出た際、その理由が正当と認められる場合(裁判所の許可が必要です)。
②成年後見人が解任される場合
成年後見人に不正行為や著しい不適切な行動があった場合、または後見の業務を適切に遂行できない事由があった場合(例えば、横領や利益相反といった不正行為や権限の濫用、任務の怠慢など)。
(2)成年後見人の職務
成年後見人の職務には以下の3つがあります
| ①財産管理 | 成年後見人は本人に代わって財産を管理します。具体的には年金の受領、預貯金の管理、収支の把握などが含まれます。また、契約の締結や取り消しも行います。 |
|---|---|
| ②身上監護 | 成年後見人は本人の安全と健康を守るため、住まいの確保、介護保険サービスの契約、施設や病院の入退院手続きを行います。 |
| ③職務内容の報告 | 成年後見人は、財産管理や身上監護の状況を家庭裁判所に年1回報告する必要があります。報告内容には後見等事務報告書、財産目録、預貯金通帳のコピー、本人収支表などが含まれます。報告により、家庭裁判所は成年後見人の職務を監督します。 |
(3)成年後見人の権限
成年後見人には以下の権限があります
- ①代理権:本人からの委任状なしで契約を締結できる
- ②取消権:本人が結んだ契約を取り消せる
- ③財産管理権:本人に代わり財産の管理や処分ができる
ただし、以下の制約があります
- ①居住用不動産の処分: 本人の居住用不動産を処分するには家庭裁判所の許可が必要です。ただし、居住用でない不動産の処分には制約がありません。
- ②利益相反: 本人と成年後見人が利益相反する場合には、特別代理人を選任するか、成年後見監督人が代理を務めることになります。
(4)成年後見人の職務・権限に含まれないこと
成年後見人の職務には以下のことは含まれません。
- ①日常の家事: 食事のサポートや掃除、買い物などの家事や介護は成年後見人の職務ではありません。
- ②医療行為への同意: 手術に対する同意などの医療行為については、本人または家族が行います。
- ③身元保証: 賃貸契約や施設の入居契約時の身元保証は成年後見人の権限には含まれません。
- ④身分行為や遺言書の作成: 結婚、離婚、遺言書の作成などは本人自身が行わなければなりません。
4.成年後見制度の手続き
(1)任意後見の場合
任意後見を利用する場合、以下の手続きが必要です
- ①任意後見契約を結ぶ: 任意後見では、元気なうちに任意後見人を選び、契約を結びます。公正証書での契約が法律で定められています。
- ②任意後見監督人の選任を裁判所に求める: 本人の判断力が低下した場合、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立てます。任意後見監督人は専門職の第三者が一般的です。
(2)法定後見の場合
法定後見で後見人を選ぶ場合、以下の4ステップを踏みます。
- ①申立準備: 家庭裁判所に申立書や医師の診断書、後見人候補者の同意書などを提出します。
- ②審理: 裁判所が申し立て内容を審理し、調査官が事情を確認します。
- ③審判: 成年後見の必要性が認められた場合、裁判官が審判を下します。
- ④後見登記: 審判が確定した後、法務局で後見登記を行います。
5.成年後見制度にかかる費用
成年後見制度の利用には以下のような費用がかかります
- ①申立手数料: 法定後見の場合、家庭裁判所に申し立てる際に手数料が必要です。通常は数千円程度です。
- ②成年後見人の報酬: 成年後見人には報酬が支払われることがあります。報酬額は家庭裁判所が決定し、月額で数万円程度になることが多いです。後見人の報酬は財産から支払われるため、本人の財産に応
- じた負担が求められます。
- ③弁護士費用: 弁護士が成年後見人になる場合、弁護士費用が発生します。これも家庭裁判所が決定しますが、一般的には数万円から十数万円程度です。
- ④公正証書作成費用: 任意後見契約を結ぶ際には公正証書を作成するため、数万円の費用がかかります。
- ⑤登記費用: 後見登記の際にも、登記にかかる費用が発生します。
成年後見制度は、判断能力が不十分な方にとって重要なサポートを提供する制度です。適切に利用することで、本人の権利を守り、安心した生活を支援することが可能です。もし将来的にこの制度を利用する可能性がある場合は、事前に情報を集めておくことが大切です。