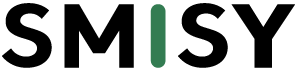認知症などで判断力が衰えると、自分の財産の管理が難しくなります。そんなときに頼りになるのが「家族信託」です。家族信託とは、信頼できる家族に自分の財産の管理や運用を託ける制度で、今回はそのメリットや注意点、手続き方法について詳しく説明します。
目次
1.家族信託とは?
「もし自分が認知症になったら、お金の管理は誰に頼めばいいの?」という不安を抱えるシニア世代や、「親が認知症になったときの財産管理はどうする?」と心配する子世代の方も多いでしょう。認知症になると預金が引き出せなくなるという話も耳にしますが、その不安を解消するための方法が「家族信託」です。
「家族信託」とは、万が一認知症などで自分の財産が管理できなくなった際に、財産の管理や処分などをできる権限を信頼する家族に与える信託契約です。この家族信託という言葉は公的な表現ではなく、「民事信託」のうち、家族に財産管理を依頼する場合のことを指す通称です。
家族信託では、「委託者」「受託者」「受益者」の3者が関与します。委託者が信頼する家族に財産の管理を依頼し、その家族が受託者となります。受託者は財産を管理・運用し、その利益を受け取るのが受益者です。委託者と受益者が同じ人であることもあります。
家族信託は、財産の所有者が何らかの理由で管理や処分が難しくなったときの備えとして利用されます。たとえば、「認知症対策がしたい」「親名義の家を将来売却したい」といったケースや、「障害のある子どもがいる」場合などに役立ちます。
2.家族信託のメリットと注意点
家族信託には多くのメリットがありますが、注意点もいくつかあります。ここではその両方を詳しく見ていきましょう。
(1)家族信託のメリット
①財産の柔軟な管理が可能
家族信託を設定しておくと、財産の所有者が病気や認知症で管理が難しくなった場合でも、信託した家族が柔軟に管理できます。たとえば、認知症になって銀行口座からの引き出しや不動産の売却が難しくなった場合でも、受託者がこれらの行為を行うことができます。
② 遺言としても機能する
家族信託は生前の財産管理だけでなく、死亡後に誰に財産を承継するかについても信託契約で指定することができます。家族信託は本人が生きている間に財産を継承できる相手を選べるという点で、生前贈与に近い面があります。ただし、生前贈与は贈与税がかかり、相続税よりも高い税率で課税されることもあります。
③ 次世代への相続も指定できる
家族信託では、委託者が複数世代先まで相続先を指定できます。受益者が亡くなった場合の次の受益者を設定することで、遺言書では指定できない二次相続以降の計画も可能です。
(2)家族信託の注意点
① 節税効果は限られている
家族信託には節税効果はほとんどありません。受託者は管理する財産に対して所得税や住民税を支払う義務がありますが、これは家族信託の有無にかかわらず発生します。また、受益者が利益を受け取る場合には贈与税がかかることもあります。
② 損益通算ができない
家族信託では、信託した不動産から生じた損失を、信託した財産以外から生じた利益と相殺することはできません。たとえば、複数の不動産を所有している場合、信託した不動産で赤字が出ても、他の不動産の黒字と差し引くことはできません。
③ 受託者の使い込みリスク
受託者が財産を使い込むリスクがあります。このリスクには、「信託監督人」や「受益者代理人」を選ぶことで対処可能です。信託監督人は信託財産が適切に管理されているかを監視し、受益者代理人は受益者の権利を代わりに行使します。
3.家族信託の手続きの流れ
家族信託を実施する際には、以下のステップを踏む必要があります。
(1)信託契約の締結
まず、財産の所有者が信託する相手を家族の中から選び、信託契約を結びます。信託契約書には契約の趣旨や目的、委託者、受託者、受益者、信託する財産などを明記します。この信託契約書を公証役場で公正証書として作成することで、高い証明力が得られます。
(2)信託用の銀行口座の開設
現金や預金を信託する場合、信託財産専用の銀行口座を開設する必要があります。受託者が自分の口座で管理することはできません。
(3)不動産の名義変更
不動産を信託する場合、法務局での登記が必要です。信託登記と所有権移転登記を行い、不動産の名義を現在の所有者から受託者に変更します。
信託登記は、家族信託の契約内容を記録するための登記です。信託登記によって受託者はどのような理由で当該不動産を管理しているのかを公示します。所有権移転登記は、家族信託をした不動産の登記名義を変更するための手続きです。所有権移転登記を行わないと、受託者は家族信託により当該不動産を管理していることを第三者に対して主張できません。
(4)信託財産の運用開始
銀行口座や不動産の手続きが完了したら、受託者は信託財産の運用を開始できます。
4.手続きにかかる主な費用
家族信託の手続きにはいくつかの費用がかかります。
(1)公正証書の作成費用
公正証書は信託契約を法的に証明するための文書で、公証役場で作成します。作成費用は信託する財産の額(目的の価額)によって異なります。
- 100万円以下:5,000円
- 100万円超え200万円以下:7,000円
- 200万円超え500万円以下:11,000円
- 500万円超え1,000万円以下:17,000円
- 1,000万円超え3,000万円以下:23,000円
- 3,000万円超え5,000万円以下:29,000円
- 5,000万円超え1億円以下:43,000円
- 1億円超え3億円以下:43,000円に超過額5,000万円までごとに13,000円を加算した額
- 3億円を超え10億円以下:95,000円に超過額5,000万円までごとに11,000円を加算した額
- 10億円を超える場合:249,000円に超過額5,000万円までごとに8,000円を加算した額
(2)不動産の登記費用
不動産を家族信託するときの信託登記には登録免許税がかかりますが、所有権移転登記には税金はかかりません。登録免許税は土地と建物で異なり、固定資産評価額に基づいて計算されます。
| 土地 | 固定資産評価額 × 0.3% |
|---|---|
| 建物 | 固定資産評価額 × 0.4% |
固定資産税評価額とは、各市区町村が、固定資産評価基準に従って個別に決定した不動産の価値の評価額のことです。この評価額は、毎年送られてくる固定資産税の納税通知書に同封されている課税明細書で確認できます。
(3)専門家への報酬
家族信託を設定する際には、信託契約書の作成や信託登記・所有権移転登記の登記手続きには司法書士や弁護士などの専門家に依頼することが一般的で、その報酬は信託財産の価額に応じて決まります。報酬は信託財産の価額によって異なり、1億円以下の場合は1%、1~3億円の場合は0.5%です。一般的に、最低でも30万円程度はかかります。
(4)信託監督人や受益者代理人への報酬
信託契約に基づき信託監督人や受益者代理人に報酬を支払う必要があり、相場は月額1万円程度です。
5.専門家への相談を早めに
家族信託は財産の管理や運用において非常に有効な手段ですが、制度内容や手続きが複雑であるため、専門家の助けが必要です。家族信託は元気なうちに準備する必要がありますので、早めに家族と相談し、信頼できる専門家に依頼することをおすすめします。専門家選びは、実績や経験を確認して慎重に行いましょう。