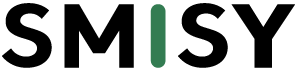認知症の親の不動産を売却することはできるのでしょうか?この疑問を持つ方も多いかと思います。認知症の親の代わりに不動産を売却することは可能ですが、成年後見制度を利用する必要があります。この記事では、認知症の親の不動産を売却する際に利用できる制度について、そのメリットや注意点を詳しくご紹介します。
目次
1.認知症の親の不動産は勝手に売却できない
認知症の親が介護施設に入ることになり、自宅が空き家になることがあります。このような場合、親名義の不動産をどう扱うべきか悩む方も多いのではないでしょうか。
日本の法律では、認知症などで意思能力がないと判断される人が自ら売買契約を結ぶことは無効とされています。意思能力とは、自分の行動が法的にどのような意味を持つかを理解する力を指します。そのため、重度の認知症の場合、本人が不動産の売買契約を結ぶことは難しくなります。
また、認知症の親に代わって子どもが勝手に不動産を売却することもできません。これは、親が意思能力を欠いているため、正式な代理人として売買契約を結ぶための同意を得ることができないからです。
ただし、軽度の認知症で意思能力があると判断される場合には、不動産の売却が可能なケースもあります。しかし、これらの例外に該当しない場合、どのようにして不動産を売却すれば良いのでしょうか?ここからは、認知症の親が所有する不動産を売却するために利用できる制度について、そのメリットや注意点を解説します。
2.認知症の親の不動産売却を可能にする「成年後見制度」
認知症が進行して意思能力が低下した親に代わって不動産を売却するための方法として、「成年後見制度」があります。この制度について詳しく見ていきましょう。
(1)成年後見制度とは?
成年後見制度とは、認知症や知的障害などで意思能力が十分でない人に代わり、成年後見人が法律行為を行う制度です。この制度を利用すれば、本人に代わって契約を結ぶことができ、不利益な契約を取り消すことも可能です。また、認知症が進行して遺産分割協議をすることが難しい相続人がいる場合には、相続人がこの制度を利用することで相続手続きを進めることができます。
成年後見制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類があります。法定後見制度は、家庭裁判所が後見人を選ぶ制度で、任意後見制度は、本人が意思能力を有するうちに将来のために後見人を選んでおく制度です。
法定後見人には、親族や司法書士、弁護士、社会福祉士などが、本人との利害関係や経歴などをもとに裁判所によって選ばれます。未成年や破産者、本人に対して訴訟歴のある者などは後見人にはなれません。親族でも、財産を不正に利用する恐れがある場合は選ばれないこともあり、この場合、異議を申し立てることはできません。
成年後見制度は、本人の利益を保護するための制度であり、不動産売却が必要な場合に利用できます。売却時には、売却価格を安くしすぎたり、成年後見人の私利私欲のために売却益を使ったりしないよう注意が必要です。居住用不動産を売却する場合には、家庭裁判所の許可が必要です。
(2)法定後見制度にかかる費用
法定後見制度を利用するには、家庭裁判所に申し立てを行う費用と、法定後見人に支払う報酬がかかります。主な費用は以下の通りです。
①申立て時にかかる費用
- 申し立て手数料:800円
- 登記手数料:2,600円
- 郵送料:約数千円
- 鑑定料:10万~20万円(本人の意思能力を確認するために必要な場合)
②法定後見人に支払う費用
法定後見人に対して報酬を支払う必要がある場合、家庭裁判所の判断により、本人の財産から月額2~6万円程度の報酬を支払います。
3.法定後見制度のメリットと注意点
ここでは、法定後見制度を利用する際のメリットと注意点について解説します。認知症の親の不動産を売却したい方は、これらの情報を参考にしてください。
(1)法定後見制度のメリット
法定後見制度の利点は以下の通りです。
①重度の認知症の親に代わって不動産を売却できる
重度の認知症を患っている場合、法定後見制度を利用することでしか親に代わって不動産を売却することができません。そのため、親の介護費用が多く必要なときや、介護施設への入居のために不動産を売却したい場合には、この制度が有効です。
②親が生存中に不動産売却を行える
生前に不動産を売却することで、固定資産税や都市計画税などの税金や不動産の維持管理費用の負担を減らすことができる可能性があります。
③本人が結んだ不利益な契約を無効にできる
悪徳商法や詐欺などの不当な勧誘で本人が不利益な契約を結んでしまった場合も、法定後見人がその契約を解除することが可能です。この契約の無効化は、任意後見制度や後述する家族信託の制度では行えないため、法定後見制度ならではの利点と言えるでしょう。
(2)法定後見制度の注意点
法定後見制度を利用する際の注意点は以下の通りです。
①家庭裁判所への申し立てが必要
法定後見制度を利用するには、まず家庭裁判所に申し立てを行わなければなりません。
②後見人に親族が選ばれないことがある
家庭裁判所は後見人として親族を選ばず、第三者を選ぶ場合があります。
③法定後見人が選任されるまで時間がかかる
法定後見人が選ばれるまでには一定の時間がかかることが多いです。
④専門家が後見人になると報酬が発生する
後見人として親族ではなく、弁護士や司法書士などの専門家が選ばれた場合、親が亡くなるまで報酬を支払う必要があります。
⑤家庭裁判所が不動産売却を許可しない場合がある
家庭裁判所が不動産の売却を認めない場合もあります。
法定後見人の役割は、本人の意思能力が不十分な場合に財産を適切に管理することです。そのため、特に正当な理由がない限り、不動産売却が許可されない場合もあります。このような事態を避けるためには、不動産を売却したい理由を明確にし、その売却が本人にとってどのような利益をもたらすかを証明する準備をしておくことが重要です。
4.判断能力がある場合には家族信託を活用
親がまだ意思能力を持っている場合、認知症が進行する前に「家族信託」を活用するのも一つの手です。ここでは、家族信託の特徴についてご紹介します。
(1)家族信託とは?
家族信託とは、信頼できる家族に自分の財産に関する権限を与え、財産の管理・処分・運用を依頼する制度です。この家族信託という言葉は公的な表現ではなく、「民事信託」のうち、家族に財産管理を依頼する場合のことを指す通称です。
(2)家族信託のメリット
家族信託を利用することには、以下のような利点があります。
①ランニングコストをかけずに済む
家族信託の大きなメリットの一つは、ランニングコストがかからないことです。この制度では家族間で信託契約を結ぶため、法定後見制度のように後見人となる専門家に報酬を支払う必要がありません。
②財産管理の方法が柔軟である
家族信託では、契約時に定めた信託目的の範囲内であれば、財産の管理方法を柔軟に決めることができます。たとえば、親が不動産を積極的に活用したいと望んでいる場合、その意向が契約に記載されていれば、不動産を売却するだけでなく賃貸経営を行うことも可能です。
その他にも、家庭裁判所への申し立てが不要であることや、親が亡くなる前に不動産を売却できる点などがメリットとして挙げられます。
(3)家族信託の注意点
家族信託には多くのメリットがありますが、以下のような注意点を理解した上で検討することが重要です。
①信託契約時に費用が発生する
不動産を信託財産に含める場合、不動産の名義を変更する必要があります。その際、名義変更に伴う登録免許税がかかります。また、信託した資金を管理するために金融機関で正式な信託口座を開設する際には、公正証書の作成が必要です。これらの名義変更や書類作成の手続きを司法書士や弁護士などの専門家に依頼する場合、別途報酬が必要になります。
②受託者の選定における親族間の争いの可能性
受託者とは、信託契約に基づき財産の管理や運用を担当する人のことです。この受託者を誰にするかを決める際、親族間で意見が対立し、争いに発展することがあります。こうしたトラブルを避けるためにも、冷静で慎重な話し合いが求められます。
③相談できる専門家の不足
家族信託は比較的新しい制度であるため、経験豊富な専門家が少ないという問題があります。それにもかかわらず、家族信託には特有の税金や法的な解釈が必要となる場合が多いため、できるだけ実績のある専門家に相談することが望ましいです。
5.法定後見制度を活用した不動産売却のプロセス
ここからは、法定後見制度を利用した場合の不動産売却の具体的な手順についてご説明します。不動産売却の流れを事前に理解し、スムーズな手続きを進めましょう。
(1)家庭裁判所への申し立て
まず、必要な書類や費用を事前に用意し、本人の住所地を管轄する家庭裁判所に対して成年後見制度の開始を申し立てます。申し立てを行うことができるのは、本人、配偶者、四親等内の親族、または検察官などです。手続きの詳細については裁判所のホームページで確認できます。また、どの家庭裁判所が管轄するかもサイトで調べることができます。
(2)家庭裁判所による審理
申し立てが行われた後、家庭裁判所は法定後見制度を利用してよいかどうかの審理を行います。審理の過程では、裁判所の職員が本人、後見人候補者、申立人に対してヒアリングを行い、必要に応じて医師による意思能力の鑑定が行われます。
(3)法定後見人の選定
家庭裁判所は、法定後見人として最も適任な人物を選任します。選任までには申し立てから約2か月ほどかかるのが一般的です。場合によっては親族ではなく、司法書士や弁護士などの専門家が後見人に選ばれることもあります。その場合、後見人に報酬が発生する可能性があるので注意が必要です。
(4)査定と媒介契約の締結
法定後見人が選任された後の手続きは、通常の不動産売却と同じです。まず、不動産の査定を受け、その後、信頼できる不動産会社と媒介契約を結びます。不動産会社の選定においては、担当者の対応や査定額の根拠が明確かどうかを確認することが重要です。
(5)居住用不動産の場合の家庭裁判所の許可
売却する不動産が本人の居住用である場合、家庭裁判所から売却の許可を得る必要があります。この許可を得ずに売買契約を結ぶと契約は無効になるため、十分な注意が必要です。許可を申請する際に必要な書類は以下の通りです。
- ①申立書
- ②全部事項証明書
- ③固定資産評価証明書
- ④売買契約書の案
- ⑤査定書
非居住用の不動産を売却する場合には家庭裁判所の許可は不要ですが、売却の正当な理由として医療費や施設入居費の確保が求められます。
(6)売買契約の締結
家庭裁判所の許可が下りた後、法定後見人が本人の代理として買主と売買契約を結びます。売買契約は、売主、買主、そして仲介する不動産会社の三者で行い、重要事項説明書の読み合わせを行った後、署名・押印をして手付金を受け取ることで完了します。
(7)決済と引渡し
引渡し当日には、残代金の受領、固定資産税などの清算、そして登記申請の手続きを行います。通常、引渡しと決済は同日に行われ、物件が買主に引き渡された時点で売却手続きは完了となります。
6.認知症の親の不動産売却に困ったら専門家に相談を
認知症の親が所有する不動産を売却したい場合、その方法は認知症の進行状況によって制約されることがあります。そのため、事前に状況に応じた売却方法を把握しておくことで、適切な手段をスムーズに選ぶことができます。特に、重度の認知症で意思能力がないと判断された場合は、法定後見制度の利用が必要となるため、認知症を発症する前に家族信託を結んで備えておくことをおすすめします。
法定後見制度を利用する場合、多くの書類を準備する必要があり、専門的な知識が求められることが多いです。そのため、専門家や認知症の家族を持つ人をサポートする不動産会社に相談するのが賢明です。
一方で、家族信託を利用する場合は、家族間で信託契約を結ぶため、受託者への報酬や家庭裁判所への申し立てが不要です。ただし、手続きが複雑で、相談できる専門家が少ないという課題があります。そのため、家族信託を検討する際は、信頼できる専門家を選ぶことが重要です。
まとめ
認知症の親の不動産を売却するには、成年後見制度の利用が不可欠です。制度の仕組みや流れを理解し、専門家のサポートを受けながら進めることで、親の利益を守りつつ適切な手続きを行うことができます。必要に応じて家族信託も検討し、安心して親の財産を管理できるようにしましょう。