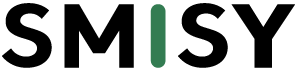サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)とは? その特徴とメリット・デメリットを詳しく解説
シニア向けの住宅や施設のひとつとして、サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)があります。しかし、そのメリットや他の施設との違いがよくわからないという方も多いかもしれません。この記事では、サ高住の特徴についてわかりやすく解説します。また、サ高住の探し方や入居までの大まかな流れもご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
目次
サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)とは?
1.サ高住とは?
サ高住は、主に要介護度が高くない60歳以上の自立した高齢者を対象とした住宅です。一般の住宅のように自由な生活を送りながら、安否確認サービスや生活相談サービスを受けられます。
①サービス内容
ア)安否確認サービス
スタッフが定期的に部屋を訪問するタイプ、ビデオカメラや感知センサーを使うタイプ、またはその両方を併用するタイプがあります。これにより、日常の安全を確保します。
イ)生活相談サービス
生活に関する相談を受け付けます。不安や困りごと、家族への連絡など、介護業務以外の悩みにも対応します。
②スタッフの対応
これらのサービスは、介護・医療・看護の資格を持つスタッフが常駐して提供します。基本的には日中のみ対応し、安否確認サービスは夜間対応も可能ですが、別契約が必要です。
③入居条件
サ高住には、主に60歳以上で自立した高齢者が入居できます。要介護度が高くない方が対象です。
サ高住は、自立した高齢者が安心して暮らせる住まいです。自由な生活を維持しながら、必要なサポートを受けることができます。各種サービスと専門スタッフのサポートにより、安全で豊かな生活が実現します。
2.サ高住の種類
サ高住には「一般型」と「介護型」の2種類があります。
①一般型
自立した生活ができる高齢者を対象とし、提供されるサービスは安否確認と生活相談です。リハビリや介護は外部業者と別契約となります。
②介護型
厚生労働省に「特定施設入居者生活介護」として指定された施設で、介護付き有料老人ホームと同様に介護や認知症対応が可能です。安否確認や生活相談に加え、介護、リハビリ、レクリエーションなどのサービスを提供します。
3.サ高住の入居条件
サ高住への入居には、三つの条件があります。自分が該当するか確認しましょう。
①入居者本人の条件
ア)一般型
基本的に60歳以上で自立した生活が可能な高齢者が対象です。60歳未満でも要介護1、2認定を受けていれば入居可能です。
イ)介護型
自立した高齢者が主な対象ですが、要介護5認定を受けた方も入居できる施設もあります。ほとんどの施設で連帯保証人や身元引受人が必要ですので、事前に親族などに確認してください。
②同居人の条件
同居人も条件に該当する必要があります。以下が代表的な条件です: ・入居者の配偶者 ・60歳以上の親族 ・要支援・要介護認定を受けている親族 ・特別な理由で同居が必要と知事が認める人
③退去条件に該当しないこと
以下に該当すると退去が求められることがあります: ・費用の滞納 ・要介護度の上昇や体調の悪化で入居継続が困難 ・施設や他の入居者への迷惑行為
これらの条件を確認し、サ高住への入居を検討しましょう。
サ高住の特徴(サービス内容から設備まで)
サ高住の特徴について詳しくまとめました。ここでは、オプションサービスの内容、入居時や月々の費用、スタッフの基準、設備などをご紹介します。
1.サ高住で受けられるサービス
① 介護サービス
入居後に介護が必要になった場合、外部サービスを利用します。施設によっては訪問介護やデイサービスなどを併設しており、別途契約で利用可能です。
② 健康・食事・入浴サービス
医療ケアは併設または提携医療機関で受けられます。食事や入浴サービスは、回数や利用ごとに料金を支払って契約します。
③ リハビリサービス
訪問リハビリは要介護認定と主治医の診断が必要です。通所リハビリは要支援1〜2、要介護1〜5の認定が条件です。
④ 社会参加支援サービス
施設によっては、花見や七夕まつりなどのイベント、地域社会との交流、入居者同士の交流スペースがあります。これらのサービスに力を入れていない施設もあるため、事前の確認が必要です。
サ高住では、自立した生活をサポートする多様なサービスが提供されています。
2.サ高住の費用
サ高住にかかる主な費用とその相場は以下の通りです。
①初期費用
ア)一般型
一般型のサ高住は賃貸住宅であり賃貸借契約のため、入居一時金は不要です。初期費用として敷金または保証金が必要です。目安は家賃の2~3か月分、数十万円ほどです。ただし、一部の施設では数年~数十年分の家賃を前払いするケースもあります。
イ)介護型
介護型は「利用権方式」を採用しており、有料老人ホームと同様の契約形態です。この方式では、建物に住む権利とサービスを利用する権利が一体化しており、入居一時金や前払い賃料として数十万~数千万円が必要です。
3.サ高住の人員基準
サ高住では、居住者に安否確認や生活相談などのサービスを滞りなく提供するため、ケアの専門家が日中常駐しています。医師、看護師、介護福祉士、社会福祉士、介護支援専門員、介護職員初任者研修修了者などがその役割を担います。このような職員が常駐することで、安心して生活できる環境が整えられています。
4.サ高住の設備
サ高住の個室は25㎡以上が基本ですが、条件を満たせば18㎡以上でも可能です。バリアフリー構造で、段差のない床、手すりの設置、広い廊下が求められます。加えて、台所、水洗便所、収納、洗面設備、浴室の設置が原則です。夜間の緊急対応のために、浴室や寝室には緊急通報システム、館内には見守りセンサーの設置が必要です。
サ高住とシニア向け分譲マンションとの違い
サ高住とよく比較される施設として、シニア向け分譲マンションがあります。
1.サ高住
| ①契約方式 | 建物賃貸借方式 |
|---|---|
| ②入居対象者 | 自立している高齢者 |
| ③サービス面 | 介護サービスや生活支援サービスなどは外部と別契約 |
| ④費用面 | 初期費用は比較的低く、外部サービスは利用分だけ支払い |
| ⑤生活自由度 | 高い |
2.シニア向け分譲マンション
| ①契約方式 | 所有権方式 |
|---|---|
| ②入居対象者 | 自立した高齢者から介護が必要な高齢者まで |
| ③サービス面 | 介護・医療サービスは外部事業者と別途契約 |
| ④費用面 | 高額 |
| ⑤生活自由度 | 高い |
サ高住のメリット・デメリット
サ高住を選ぶ際には、メリットとデメリットをしっかり理解しておくことが重要です。
1.サ高住のメリット
①高い生活自由度
キッチンや浴室が完備されており、生活習慣を大きく変えずに快適に過ごせます。
②低い初期費用
賃貸借契約のため、入居時の費用や月額費用が有料老人ホームなどに比べて安価です。
③柔軟なサービス選択
必要な介護サービスや生活支援サービスを選んで契約できるため、自分に合ったプランが選べます。
2.サ高住を選ぶデメリット
①夜間スタッフの常駐義務がない
サ高住では夜間のスタッフ常駐が義務付けられていません。夜間は基本的にシステムによる安否確認となります。そのため、夜間のサポートが心配な方には、24時間体制の有料老人ホームが適しているかもしれません。
②要介護度が上がると退去が必要な場合がある
要介護度があがると、退去を求められる施設が多いです。その場合、退去の通知を受け、新たな住まいを探さなければならなくなります。
③有料サービスの質に差がある
安否確認や生活相談のサービスは必須ですが、その他の有料サービスは施設によって大きな差があります。入居後の後悔を避けるためにも、事前に各施設のサービス内容を十分に調べることが重要です。
サ高住の選び方
サ高住を選ぶ際には、自分に合った施設を見つけるために以下の5つのポイントを考慮することが重要です。
1.立地・アクセス
日常的に利用する店舗や病院、銀行などの距離とアクセスの良さを確認しましょう。また、家族の住まいからの距離もチェックしておくと安心です。
2.費用
初期費用や月額費用、追加サービスの料金が予算内に収まるかを確認してください。細かくチェックすることが大切です。
3.サービスの内容
サ高住には「一般型」と「介護型」がありますので、自分に合ったタイプを選ぶ必要があります。さらに、オプションサービスの種類や質、スタッフの雰囲気も見ておきましょう。
4.居住環境・設備
居室の間取りや広さ、共用スペースの設備状況、娯楽スペースの有無などを確認しましょう。日当たりなども考慮すると良いでしょう。
5.食事
献立内容だけでなく、食事の提供方法やスタッフの対応もチェックして、食事の質を確認することが大切です。
サ高住への入居までの流れ
情報収集から入居までの流れと重要な注意点を詳しく説明します。
1.情報収集・資料請求・問い合わせ
インターネットの検索サイトや市町村の情報を活用して、サ高住を効率的に探します。興味がある施設が見つかったら、ホームページや電話から資料を請求しましょう。また、介護認定を受けている方は、担当のケアマネジャーに相談するのも良い方法です。各自治体のホームページには、サ高住の重要事項説明書が掲載されている場合がありますので、資料と合わせて確認しておくと安心です。
2.見学・体験入居
候補となる施設が決まったら、実際に見学に行きましょう。見学では、建物の設備、スタッフの雰囲気、サービス内容、食事の質、日当たり、レクリエーションの様子など、資料ではわからない詳細な情報を得ることができます。複数の施設を見て、サービスの違いを比較するのが良いでしょう。また、体験入居が可能かどうか確認し、実際の生活を体験してから決断するのが安心です。体験後は、家族と感想を共有し、施設選びに役立てましょう。
3.仮申し込み・書類審査・面談
施設を決定したら、申込書に記入して仮申し込みを行います。この際、連帯保証人や身元引受人の情報も必要ですので、事前に確認しておきましょう。施設側では、書類審査の他に、入居者と家族への面談が行われ、身体状況や入居後の希望についてのヒアリングがあります。
4.契約
審査が通過したら、正式に申し込み、入居契約を締結します。契約書に署名押印し、必要書類と入居金を用意すれば契約完了です。不明点や不安な点がある場合は、契約前にしっかりと確認し、納得してから契約を進めましょう。
5.入居
入居日が決まったら、必要な手続きや準備を計画的に進めます。洗濯機などの大型家電は共用のことが多いですが、居室内の生活用品は自分で準備する必要があります。事前に施設に詳細を確認し、安心して入