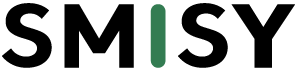シニア向け賃貸住宅とは? その特徴とメリット・デメリットを詳しく解説
シニア向けの住まいのひとつとして、シニア向け賃貸住宅があります。しかし、そのメリットや他の施設との違いがよくわからないという方も多いかもしれません。
この記事では、シニア向け賃貸住宅の特徴についてわかりやすく解説します。また、シニア向け賃貸住宅の探し方や入居までの大まかな流れもご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
目次
シニア向け賃貸住宅とは?
シニア向け賃貸住宅とは、60歳以上の元気なシニアの方々が、仕事や趣味を楽しみながら安心して暮らせるように設計された賃貸マンションです。民間企業が運営しており、シニア専用に特化したさまざまなサービスが提供されています。
シニア向け賃貸住宅は、介護が始まる前の「プレ介護」としての住まいであり、介護施設への入居に抵抗を感じるご家族や高齢者にとって、敷居が低く安心できる住まいです。施設のような堅苦しさがなく、よりリラックスして老後を迎えられる場所と言えます。
シニア向け賃貸住宅の特徴
シニア向け賃貸住宅は、一般的なマンションと同様に完全個室で、トイレや浴室、キッチンが完備されています。これにより、自分のペースで自由に生活を楽しむことができます。プライバシーがしっかり守られているため、自分の時間を大切にしたい方や介護が必要ない方に最適な住まいです。
1.特徴
シニア向け賃貸住宅は、介護が不要な高齢者が安心して生活できるように設計されたバリアフリー対応の施設です。段差がなく、安心して生活できるよう配慮されています。
2.入居条件
原則として60歳以上の方が対象です。また、介護が必要ない元気な方が入居できます。
3.費用
| 敷金 | 家賃の2~3ヵ月分 |
|---|---|
| 月額費用 | 10~50万円 |
| 管理費 | 2万円~ |
※物件によって異なります
4.居室面積
個室の広さは原則として25㎡以上ですが、条件を満たせば18㎡以上の部屋もあります。
5.主なサービス
安否確認、緊急対応、生活相談(提携病院の紹介や介護サービスに関する相談など)が提供されます。
6.契約方式
建物賃貸借契約で、一般の賃貸住宅と同じ方式で契約します。
7.食事・介護サービス
食事や介護が必要になった場合は、外部の有料事業者が提供するサービスを利用できます。必要に応じて、食事の提供を受けながら生活を続けることが可能です。
シニア向け賃貸住宅は、サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)とは異なり、レストランや日常生活のサービス、介護サービスが必ずしも提供されるわけではありません。自分のライフスタイルに合わせて、必要なサービスを選んで利用することができます。
シニア向け賃貸住宅のメリット
シニア向け賃貸住宅は、全てのシニアに適しているわけではありません。住環境を選ぶ際には、シニア向け賃貸住宅のメリットとデメリットをしっかり把握し、総合的に判断することが大切です。ここでは、主なメリットについてご紹介します。
1.高齢者でも入居しやすい
通常の賃貸住宅では、高齢者の入居を断られる場合があります。これは、契約者が亡くなった場合に「事故物件」として扱われ、次の借主を見つけるのが難しくなるからです。これに対して、シニア向け賃貸住宅は最初から高齢者を対象にしているため、高齢者の入居がスムーズに進みます。この点が、シニア向け賃貸住宅の大きな魅力です。
2.自立した生活が可能
介護が必要な方が入居する施設では、外出や自炊の制限、入浴時間の指定など、生活に制約があることが一般的です。しかし、シニア向け賃貸住宅では、元気なシニア層を対象としており、自立した生活をサポートします。プライバシーが守られ、自由な生活が送れるため、今まで通りの自立した生活を維持しながら、万が一の事態に備えることができます。
3.外部サービスの利用が可能
シニア向け賃貸住宅では、入居後に介護が必要になった場合でも、外部サービスを利用することで対応できます。これにより、介護が必要になっても、住み慣れた場所での生活を続けることが可能です。また、一部のシニア向け賃貸住宅では食事の提供や掃除などのサービスも受けられますが、これらは物件によって異なるため、具体的なサービス内容を確認してから入居を決めることが重要です。
4.住居費を抑えられる
持ち家で一人暮らしをしていると、住宅ローンの返済、固定資産税、都市計画税、修繕費などの支出が発生します。一方、シニア向け賃貸住宅では、毎月の家賃が必要ですが、固定資産税や修繕費などは貸主が負担します。また、賃貸マンションは一人暮らし向けに設計されており、無駄なスペースが少なく、管理もしやすい点もメリットです。
シニア向け賃貸住宅は、生活の自由度が高く、外部サービスを利用することで安心して暮らし続けることができます。また、経済的な負担も抑えられるため、多くのシニアにとって魅力的な選択肢となるでしょう。
シニア向け賃貸住宅のデメリット
シニア向け賃貸住宅には、以下のようなデメリットがあります。
1.永住できるとは限らない
一般的な賃貸住宅では、家賃をきちんと支払っていれば、原則として永住が可能です。しかし、シニア向け賃貸住宅では、永住できる保証がありません。例えば、介護が必要になったり、認知症が進行した場合、マンションのサポート体制が不十分なため、退去を求められることがあります。このような場合、サポートが充実した施設への移行が必要になるため、事前にサポート体制について確認しておくことが重要です。
2.家賃負担が発生する
シニア向け賃貸住宅には、毎月の家賃が必要です。これが一般的な賃貸住宅よりも高めに設定されていることが多く、生活費の負担が増す可能性があります。退職後は年金生活になるため、年金だけで家賃を賄えない場合は、貯金を使う必要があります。さらに、介護が必要になったり、病気になると追加の支出が発生することもあります。そのため、無理のない家賃設定であるかどうかを慎重に検討してから入居を決定することが重要です。
シニア向け賃貸住宅を選ぶ際には、これらのデメリットをしっかりと理解し、自分の生活設計に合った選択をすることが大切です。
シニア向け賃貸住宅の選び方
高齢者が賃貸物件を選ぶ際には、以下のポイントに注意することが重要です。
1.医療機関が近いか
年齢とともに病気や体力の衰えが進むため、医療機関へのアクセスが重要です。物件から病院までの距離が短いと、通院が楽になります。かかりつけ医がいる場合は、その近くに住むことで、安心して医療サポートを受けられるでしょう。
2.家族が近くに住んでいるか
日常生活でのサポートは、家族が近くに住んでいると心強いです。年齢を重ねると、買い物や掃除などの作業が難しくなることがあります。家族が近くにいることで、急なトラブルや体調不良の際に助けてもらえる可能性が高くなります。
3.利便性が高いか
高齢者は移動範囲が狭くなることがあるため、利便性の高い物件を選ぶことが大切です。スーパーや銀行、駅やバス停に近い物件なら、日常生活が便利になります。行動範囲が限られても、生活に困らないよう利便性の高い物件が理想です。
4.バリアフリー対応か
体力の衰えを考慮すると、バリアフリー対応の物件が望ましいです。段差が少なく、車いすの利用が可能な設計や、エレベーターのある物件は、将来の生活が楽になります。バリアフリー対応の物件選びは、高齢者にとって重要なポイントです。
5.動線が利用しやすいか
物件の動線がシンプルであることも重要です。トイレや水回りなど、頻繁に使用する場所へのアクセスが簡単であれば、掃除や管理がしやすくなります。活動範囲が狭くなっても快適に過ごせるよう、動線を意識した間取りの物件を選びましょう。
6.安全性が高いか
安全性も考慮するべきです。周囲が暗く、誰でも自由に出入りできる物件は避けた方が良いでしょう。明るく人通りが多い場所に位置する物件や、オートロック付きで安全性の高い物件が安心です。TVモニター付きインターホンなど、セキュリティ設備が整った物件もおすすめです。
7.家賃設定に無理がないか
退職後は収入が限られるため、家賃設定にも注意が必要です。退職金があるうちは良いですが、年金生活に入ると家賃負担が重くなる可能性があります。長期間にわたり無理なく支払える家賃の物件を選び、将来の医療費や介護費用も考慮して選びましょう。
これらのポイントを踏まえて、自分に合った賃貸物件を選ぶことで、安心で快適な生活を実現できます。
シニア向け賃貸住宅に住むまでの流れ
シニア向け賃貸住宅の契約入居までの流れ
1.見学日を決める
見学したい建物、部屋が決まりましたら、見学希望日を連絡します。
2.現地見学
実際に、部屋の雰囲気・周辺環境を見学します。
3.申込み
お気に入りの部屋が見つかったら、申込みをします。
(申込みに必要な書類)
- 賃貸住宅入居申込書(連帯保証人、身元引受人の記入が必要)
- 申込書記入者の本人確認資料の写し(健康保険証や運転免許証など)など
4.入居審査
運営会社による審査結果が行われます。
5.賃貸借契約
入居可能と判断された場合、運営会社による重要事項説明が行われたあと、賃貸借契約を締結します。契約締結後「引越しの手順」「みまもりサポート」「電気」「ガス」「水道」など入居までに必要な説明が行われます。
6.入居
入居日までに必要な手続きや持ち物を運営会社に確認し、計画的に準備を進めましょう。新しい生活のスタートに向けて、しっかりと準備を整えてください。